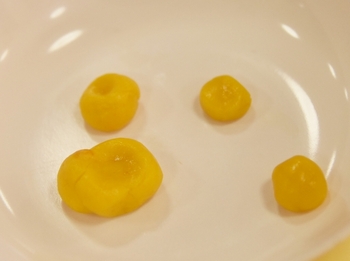園の風景
最近の記事
納豆づくり 【2024年3月12日】
年長さんの中から希望者を募り、今年も納豆づくりを行いました。

一晩たっぷりの水を吸い、ぷっくりとした大豆を、茹でた稲わらに詰めていきます。
お話を聞いて、「それだけで納豆ができるの?」とびっくりしている子もいました。


 稲わらにいる納豆菌が、大豆を納豆に変身させてくれるということを知り、「美味しくなりますように」とみんなでお願いしました。
稲わらにいる納豆菌が、大豆を納豆に変身させてくれるということを知り、「美味しくなりますように」とみんなでお願いしました。
新聞紙にくるんだら、電気毛布で包み込み、丸二日間発酵させます。
 発酵して、納豆の粘り気が出てきました。
発酵して、納豆の粘り気が出てきました。
年長さんに、完成したわら納豆を見せて、作ったみんなでいただきました。

「すごい!納豆できてるー!」「自分で作ったから美味しい」という声が上がったり、

「いつもの納豆と味が違う」「藁の味なのかな?」とわら納豆ならではの味わいを感じたり、

「もっと食べたかったー!」「また作りたい!」と言ってくれる子たちもいました。

「ごちそうさまでした!」「ありがとうございました!」
きちんと挨拶してくれる素敵な年長さんたちでした。
幼稚園生活もあと少し。
たくさんの思い出を作ってほしいと思います。
稲わらなっとう作り 【2023年2月28日】
2月20日、今年度もまどか幼稚園で納豆作りをおこないました。
参加するのは、納豆作りをしたいと希望して、紙に名前を書いて提出した年長組の子ども達です。
材料はお米を収穫した後の稲わらと大豆の2つ。
宮城県の雁音農産の小野寺さんからいただいた稲わらでわらつとを作り、沸騰したお湯で数分消毒。
稲の中には納豆菌が多く存在し、わら1本に生きている菌はなんと1000万以上。
茹でることで他の菌はなくなりますが、熱に強い納豆菌はわらに残ります。 子ども達は順番に、茹でた大豆をわらつとの中に入れて...
子ども達は順番に、茹でた大豆をわらつとの中に入れて...
大豆でいっぱいになったらわらを折り曲げふたをして、新聞紙でくるっと包みます。
 電気毛布の中で2日間保温すると、わらの納豆菌が活性化して大豆は納豆に変身。
電気毛布の中で2日間保温すると、わらの納豆菌が活性化して大豆は納豆に変身。
糸を引く納豆ができあがっていました。 ごはんと一緒にクラスへお届けし、お昼ご飯と一緒に美味しく食べることができました♪
ごはんと一緒にクラスへお届けし、お昼ご飯と一緒に美味しく食べることができました♪

まどかみその仕込み 【2022年5月16日】
5月11日は年長組のみそ作り。
例年は年中組の3学期に作っていますが、昨年度は感染症の影響により予定の変更が重なり、進級してからおこなうことになりました。
材料は大豆・米麹・塩の3つ。
大豆は水に浸けてふくらませ、圧力鍋でやわらかく煮て、米麹と塩と一緒に袋の中に入れます。

 まずは大豆を指で狙ってつぶし、手のひら全体で混ぜて...準備完了!
まずは大豆を指で狙ってつぶし、手のひら全体で混ぜて...準備完了!
まだ全くみそには見えませんが、年長組3クラス分を合わせて、空気が入らないよう樽に入れて、冷暗所で休ませます。
発酵と熟成が順調であれば、冬のはじめ頃には出来上がるはずです。

みそ作りをはじめてから、6年目のまどかみそ。
今年も無事に完成し、美味しいお味噌汁を味わえますように。
稲わらなっとう作り 【2021年12月17日】
12月10日、年長さんが納豆作りをおこないました
材料は稲わらと大豆の2つ。
宮城県の雁音農産の小野寺さんからいただいた稲わらでわらつとを作り、沸騰したお湯で数分茹でます。
大豆は一晩水に浸してから、圧力鍋で煮て柔らかくします。
 参加するのは、納豆作りをしたいと希望して紙に名前を書いて提出した子ども達。
参加するのは、納豆作りをしたいと希望して紙に名前を書いて提出した子ども達。
クラスごとにホールに集まり、茹でたわらの中に茹でた大豆を入れていきます。
 稲の中には納豆菌が多く、わら1本に生きている菌はなんと1000万以上。
稲の中には納豆菌が多く、わら1本に生きている菌はなんと1000万以上。
新聞紙でくるっと包み、電気毛布の中で1~2日間保温すると、わらの納豆菌が活性化して大豆が納豆に変わります。
2日後にわらを開けると、糸を引く納豆ができあがっていました。
ごはんと一緒にクラスへ。お昼ご飯と一緒に美味しく食べることができました。
今年も無事に納豆を作ることができて良かったです♪

稲わらなっとう 【2021年1月 8日】
年末のことになりますが...
12月21日、年長さんが納豆作りをおこないました。
前の週に納豆のお話をして、作りたい子は申込みの紙に名前を書いて提出し、希望した子が集まります。
材料はお米を収穫した後の稲わらと、大豆。
園の田んぼの稲では足りないため、宮城県の雁音農産の小野寺さんから安心して使えるわらを分けていただきました。 稲の中には納豆菌が多く、わら1本に1000万もの菌が生きていると言われています。
稲の中には納豆菌が多く、わら1本に1000万もの菌が生きていると言われています。
熱湯でぐつぐつ茹で、稲わら(わらつと)の中にやわらかく茹でた大豆を入れて、新聞紙でくるっと包みます。 電気毛布の中で保温して48時間。あたたかいわらを開くと、大豆の色も香りも変わっていました。
電気毛布の中で保温して48時間。あたたかいわらを開くと、大豆の色も香りも変わっていました。
 ご飯の上にかけて、少しずついただきます。
ご飯の上にかけて、少しずついただきます。
大粒のわら納豆は市販の納豆に比べると香りも味も強いと思いますが、あっという間に食べ終えました。
 お米を味わうだけでなく、お米作りの副産物として稲わらも使い、稲の力をたっぷり味わいました♪
お米を味わうだけでなく、お米作りの副産物として稲わらも使い、稲の力をたっぷり味わいました♪
年長さんの稲わら納豆 【2019年12月13日】
12月11日は、稲わらの納豆作り。
お米作りの副産物である稲わらは、古くから衣食住を支える大切な素材で、納豆を作ることも出来ます。
5月からお米作りを体験してきた年長さんが、稲に触れる最後の活動です。 納豆作りをしたい年長さんは事前に名前を書いた紙を提出し、希望した子ども達はけやきルームへ。
納豆作りをしたい年長さんは事前に名前を書いた紙を提出し、希望した子ども達はけやきルームへ。
前日に束ねた稲を茹でて、大豆を柔らかくなるまで煮て、稲のわらづとの中に大豆を入れます。

 たくさん入れた大豆がこぼれないように稲で蓋をして包んだら、40度程で保温をして2日間...
たくさん入れた大豆がこぼれないように稲で蓋をして包んだら、40度程で保温をして2日間...
稲の枯草菌は今年も頑張ってくれたようで、無事に納豆へと変わっていました。
 出来上がった納豆はお昼ご飯の時間に試食。
出来上がった納豆はお昼ご飯の時間に試食。
納豆作りに参加していない子ども達も、お友達の納豆を見てみます。
初めて食べた子や、苦手だと思っていた子も、自分で作った納豆を楽しく味わい、稲の力を知ることが出来ました。



お芋掘りのさつまいもおやつ 【2018年12月 4日】
9月から10月にかけて、学年ごとにおこなったお芋掘り。
子ども達は自分で掘ったさつまいもをたくさん持ち帰りましたが、保育で使うためのさつまいもも掘り、幼稚園で寝かせていました。
すぐに食べずに保存することで、さつまいものデンプンが糖に分解され、甘さが増していくそうです。 そのさつまいもを使って、11月のきせつをたべよう☆ではさつまいものおやつを作りました。
そのさつまいもを使って、11月のきせつをたべよう☆ではさつまいものおやつを作りました。
一つ目はさつまいもとりんごのはちみつ煮。
さつまいももりんごも皮までまるごと、はちみつと水を入れたお鍋でことこと煮ます。

 二つ目はさつまいもとおからのケーキ。
二つ目はさつまいもとおからのケーキ。
蒸かしたさつまいもを軽くつぶして、卵・豆乳・さとう・おから・ベーキングパウダーと一緒にミキサーで混ぜ合わせ、オーブンで焼きます。
 どちらも秋の栄養がたくさん詰まったおやつになりました。
どちらも秋の栄養がたくさん詰まったおやつになりました。
秋の恵みをしっかり味わい、力を蓄えれば、もうすぐ来る寒い冬も元気に越せることでしょう。
きせつをたべよう☆2016年度 【2016年1月 1日】
きせつをたべよう☆2016年度
1年の活動をまとめましたのでこちらからご覧ください。
きせつをたべよう☆2016年度.pdf
きせつをたべよう☆2015年度 【2015年1月 1日】
きせつをたべよう☆2015年度
1年の活動をまとめましたのでこちらからご覧ください。
きせつをたべよう☆2015年度.pdf